在宅ワーク×フリーランスを目指す人必読!失敗しないポイントから税金まで徹底解説

在宅で働ける仕事に注目が集まり、フリーランスとして自宅を拠点に収入を得る人が増えています。時間や場所に縛られず、家庭の事情や自分のペースに合わせて働けるのは大きな魅力ではないでしょうか。一方で収入の不安定さや税金の手続きなど、事前に知っておきたい課題もあります。
本記事では、未経験から始めるポイントや仕事の選び方、収入を安定させるためのポイント、税金やインボイス制度の基本まで網羅的に解説します。在宅ワークに興味がある人や通勤が難しい事情を抱える人、自由な働き方に挑戦してみたい会社員や副業希望者にも役立つ内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。
未経験でも在宅フリーランスになれるのか?
興味はあるけれど、今からでも挑戦できるのか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。結論から言えば、何歳からでも在宅フリーランスに挑戦することはできます。なぜなら現在は、初心者向けの仕事やオンラインで学べる講座が豊富にあるからです。
例えばクラウドソーシングサイトでは、簡単なデータ入力や商品レビューの執筆など、スキルがなくても始められる案件が多数掲載されています。一般的には簡単な案件から始めて実績を積み、少しずつ専門性を高めていく方法が一般的です。
無料で使える学習プラットフォームや低価格の動画講座なども増えており、知識ゼロからでも基礎を身に付けやすくなっています。例えばWebライティングや画像編集などは、初心者でも数週間の学習で仕事につながるスキルを習得することが可能です。学びの環境が整っている点は、未経験者にとって大きな後押しになっているといえるでしょう。
ただし、始めてすぐに高収入を得るのは難しい場合もあります。小さな実績を積み重ねながら、信頼とスキルを育てていく意識が大切です。何歳からの挑戦でも、段階を踏めば形になります。焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。

在宅フリーランスのメリット3選
在宅でフリーランスとして働く主なメリットは、次の3つです。
- 場所や時間とらわれず自由に働ける
- 満員電車・通勤ストレスから解放される
- がんばり次第で高収入を得られる
それぞれ見ていきましょう。
場所や時間とらわれず自由に働ける
在宅フリーランスは、働く場所や時間を自分で選べる柔軟性があります。自宅やカフェ、旅行先など、ネット環境さえあればどこでも作業可能です。基本的に通勤が不要のため、朝の準備に追われることもなく、生活リズムに合わせてスケジュールを調整できます。
案件にもよりますが、例えば子育て中なら子どものお昼寝や登園中の時間帯に合わせて作業を進めることも可能です。日中に病院や役所に行く必要がある場合でも、自分で予定を組み替えられるため、ストレスが溜まりにくいでしょう。場所や時間の制約がないことで、日常生活と仕事のバランスを取りやすくなり、自律的な働き方を実現しやすくなります。

満員電車・通勤ストレスから解放される
毎朝の通勤ラッシュに悩まされることがないのは、在宅ワークの大きな魅力です。満員電車に長時間揺られることなく、身体的・精神的な負担を軽減できます。通勤による疲労がなくなることで仕事始めから集中力を維持しやすくなるため、生産性の向上にもつながるでしょう。
さらに通勤時間がゼロになることで1日の自由時間が増え、家事や趣味、家族との時間にゆとりが生まれます。天候に左右されることもないため、天気が悪い日でもスムーズに業務に取り組めるのも利点です。外出の準備や移動にかかっていた時間とエネルギーを有意義なことに使えるのは、在宅フリーランスならではのメリットといえるでしょう。
がんばり次第で高収入を得られる
在宅フリーランスは、スキルや努力次第で収入を大きく伸ばせる可能性があります。企業に雇用されている場合は給与が固定されていることが多く、収入アップには時間や役職の昇進が必要です。しかしフリーランスであれば、受注する案件の単価や数を自分でコントロールできます。
スキルを磨いて専門性を高めたり高品質な成果物を継続的に提供したりすることで、より高単価の案件を獲得できるチャンスが増えるでしょう。また複数のクライアントと契約したり、サービスを多角的に展開したりすることで収入源を増やし、安定した高収入を実現することも可能です。自分のがんばりがダイレクトに収入へ反映されるため、モチベーションを高く維持しながら仕事に取り組めるでしょう。
在宅フリーランスのデメリット3選
在宅でフリーランスとして活動することには、デメリットもあります。理解したうえで、対策を考えておくとよいでしょう。
- 収入が不安定になりやすい
- 仕事とプライベートの境目が曖昧になる
- すべてを1人でこなさなければならない
それぞれ解説します。
収入が不安定になりやすい
在宅フリーランスは月給制ではないため、案件の受注状況によって収入にばらつきが生じます。特に駆け出しの時期は安定した収入源が確保できず、月によって収入が大きく変動することも。体調不良や家庭の事情で作業できない期間があれば、大幅に収入が減少するケースもあるかもしれません。
また経済情勢や需要の変化によって、案件数が減ることも考えられます。このような不安定さに備えるためには貯蓄を増やす、複数の取引先と契約を結ぶ、継続案件を確保するなどのリスク分散が必要です。安心して働き続けるためにも、日頃から計画的に案件・資金管理していくとよいでしょう。
仕事とプライベートの境目が曖昧になる
自宅で仕事する場合、生活と業務の切り替えが難しくなりやすいです。例えばリビングでパソコン作業していると、家族の話し声や家事の合間に気が散ってしまうことも少なくありません。逆に業務が立て込んでくると、家事や育児の時間を削ってまで作業を続けてしまうこともあります。
このような状態が続くと疲労が蓄積し、精神的な余裕を失ってしまうことも。そのため作業スペースを家庭内で明確に分ける、業務時間を固定する、意識的に休憩を組み込むなどの対策が必要です。オンとオフを意識的に切り替えることで集中力も保ちやすくなり、仕事の質も向上します。
すべてを1人でこなさなければならない
在宅フリーランスは、自分が事業主としてすべての業務に対応しなければなりません。営業活動から案件管理、スケジュール調整や納品、請求書の作成から確定申告など、企業であれば複数の部署で分担される仕事をすべて1人で担うことになります。
想像以上に事務作業に時間を取られることもあり、本業に集中できないと悩む人も。税務や経理に不安がある場合は、フリーランス向けの会計ソフトや専門家のサポートを活用すると負担を軽減できます。限られた時間を効率的に使うためにも、作業の優先順位を明確にして定期的な見直しを心がけましょう。

未経験から在宅フリーランスを目指す人におすすめ!仕事を選ぶ5つのポイント
どのような仕事を選ぶかで、継続へのモチベーションや収入に差が出ます。未経験から在宅フリーランスの人が仕事を選ぶ際、押さえておきたいポイントは次の5つです。
- 初期投資が少なく始めやすい仕事を選ぶ
- 継続案件につながりやすいジャンルを選ぶ
- 自分の興味・強みが活かせる仕事を選ぶ
- 将来のスキルアップや転用が可能な仕事を選ぶ
- 市場ニーズが高く案件が多いジャンルを選ぶ
それぞれ解説します。
1.初期投資が少なく始めやすい仕事を選ぶ
挑戦する仕事によって、必要な初期費用は変わります。高額な機材や専門的なソフトウェアの購入、あるいは特定の資格取得に多額の費用がかかる仕事は、途中で挫折した場合の金銭的リスクが大きくなるでしょう。
例えばWebライティングやデータ入力、オンラインアシスタントなどは、基本的にパソコンとインターネット環境さえあれば始められるため、初期費用を抑えることが可能です。もし相性が合わなくても大きな損失なく方向転換できるため、始めるハードルが低く継続にもつながりやすいでしょう。スキルのない状態で始めるなら、最初は初期費用の少ない仕事から始めるのがおすすめです。
挑戦したい仕事に必要なスキルや、資格取得に高額の費用がかかる場合は、副業としてスタートしてから徐々に本格化していくとよいでしょう。金銭的スキルも軽減できますし、その仕事が自分に合っているのか、じっくり適性も見極められます。
2.継続案件につながりやすいジャンルを選ぶ
フリーランスとして安定した収入を得るためには、単発の案件だけでなく継続的な仕事につながりやすいジャンルを選ぶことが大切です。例えばWebサイトの保守・更新、企業のSNS運用代行、定期的な記事執筆などは、長期的な契約になりやすい傾向があります。
また特定の専門知識を必要とする分野、例えば企業の広報サポートや経理業務代行なども、一度任せられると継続的に依頼してもらえるケースが多いです。さらにクライアントとの信頼関係を築くことで、他の業務を紹介してもらえることも。
仕事が安定してくれば、月ごとの収入変動も緩やかになります。継続可能性の高いジャンルを選ぶことで、在宅フリーランスとしての生活基盤を築きやすくなるでしょう。
3.自分の興味・強みが活かせる仕事を選ぶ
長くフリーランスとして活躍していきたいなら、関心がある分野や得意なジャンルを選ぶとよいでしょう。興味のある分野の仕事であれば、新しい知識を学ぶことやスキルを磨くことが苦になりにくく、継続的な成長につながります。
また元々持っている知識や経験を活かせる仕事であれば、未経験であってもスタートダッシュが切りやすく、早期にクライアントからの信頼を得やすいでしょう。例えば、日頃からSNSで情報発信するのが好きならSNS運用代行、文章を書くのが得意であればWebライター、細かい作業が好きならデータ入力や事務代行など、自身の得意なことや好きなことから仕事を探してみるのがおすすめです。
4.将来のスキルアップや転用が可能な仕事を選ぶ
将来的なスキルアップや、他の仕事への転用が可能かどうかも考慮するとよいでしょう。例えばWebライティングの経験を積むことでディレクターや編集者への道が開けたり、Webデザインのスキルを習得すればWebサイトの制作全体を請け負ったりも可能です。
プログラミングや動画編集なども、一度スキルを身に付ければ時代やニーズの変化に合わせて応用できる汎用性の高いスキルといえるでしょう。今後のキャリアプランを見据えながら仕事を選ぶことで、将来の選択肢を増やせます。
5.市場ニーズが高く案件が多いジャンルを選ぶ
未経験からフリーランスを目指す場合、案件数が多く需要の高いジャンルを選ぶことで仕事を見つけやすくなります。市場ニーズが高い分野は募集されている案件も多く、初心者向けから経験者向けの仕事まで幅広く存在するため、自身のスキルレベルに合った案件を見つけやすいでしょう。
例えば、インターネットの普及によって需要が増しているWebライティングやWebデザイン、動画編集などは、常に多くの案件が募集されています。またオンライン化の普及に伴い、オンラインアシスタントや経理代行などのバックオフィス業務を請け負う仕事も増加傾向にあります。
具体的な仕事例は以下の記事で紹介しているので、併せて参考にしてください。
関連記事:在宅ワーク未経験のママ向け!おすすめの種類20選と選ぶポイント

【在宅フリーランス向け】案件探しにおすすめのサイト3選
在宅フリーランスとして仕事を始める際、最初の壁となるのが案件探しです。ここでは、おすすめのサイトを3つ紹介します。
- ママワークス
- クラウドワークス
- Cxo works
それぞれの特徴を見ていきましょう。
ママワークス
ママワークスは、主婦(夫)に特化した求人サイトです。在宅勤務や時短勤務、週1〜2日勤務など柔軟な働き方ができる案件が豊富で、初心者向けの仕事から専門スキルを活かせる仕事まで、幅広い職種が掲載されています。
企業側も子育てに理解のある企業が多いため、急な子どもの体調不良などにも対応してもらいやすい環境があるのもメリット。自分のスキルやライフスタイルに合わせて無理なく働きたいと考えている人に、ぜひチェックしていただきたいサイトです。またスカウト機能もあり、プロフィールを充実させることで企業側からオファーが来ることもあります。自分では思ってもみなかった仕事に出会えるかもしれません。
クラウドワークス
クラウドワークスは、日本最大級ともいえるクラウドソーシングプラットフォームです。ライティングやデザイン、動画編集など多様なジャンルの案件が揃っており、初心者から経験者まで幅広く利用されています。
単発の簡単なタスク案件から、長期契約を前提とした高単価のプロジェクトまで選択肢が豊富なため、自分のレベルに合った仕事が見つかりやすいでしょう。メッセージ機能や納品管理ツールも整備されており、オンラインで完結できる点も安心材料の一つです。
Cxo works
Cxo worksは、スキルや経験を活かしてフリーランスとしての幅を広げたい人に適したプラットフォームです。他のサイトと比較すると専門性の高い案件が多く、特にマーケティングや企画運営、経営支援に関するプロジェクトに強みを持っています。在宅での業務が基本で週数日〜稼働可能な案件もあるため、副業から本格的な独立まで柔軟に対応できるのも特徴です。
一定以上のビジネススキルや実務経験が求められる案件が多いですが、そのぶん報酬水準は高めに設定されており、過去の実績やキャリアを活かして専門的な仕事にチャレンジしたい人におすすめです。
在宅フリーランスとして安定収入を得るためのポイント4つ
在宅フリーランスとして長く活動を続けるには、継続的に仕事を受けられる状態を維持することが大切です。ここでは、ポイントを4つ紹介します。
- スキルを磨き続けて単価アップを目指す
- 複数のクライアントと継続的な関係を築く
- ポートフォリオや実績をこまめに更新する
- 無理なく続けられる働き方を確立する
それぞれ見ていきましょう。
1.スキルを磨き続けて単価アップを目指す
在宅フリーランスとして収入を安定させるには、スキルの専門性を高めて単価を上げていくことが不可欠です。未経験から始めた仕事でも、継続的にスキルを磨くことで高度な案件に対応できるようになり、クライアントからの信頼を得て単価交渉しやすくなります。
例えばWebライターなら、単に文章を書くだけでなくSEOの知識やインタビュー、校正のスキルを身に付けることで、より専門的な業務を任せてもらえるチャンスが増えるでしょう。Webデザインであれば、コーディングや動画編集のスキルをプラスアルファで習得することで、請け負える仕事の幅が広がり結果的に単価アップにつながります。
2.複数のクライアントと継続的な関係を築く
一つのクライアントに依存してしまうと突然の契約終了や方針変更があった際に、収入が途絶えてしまうリスクがあります。安定した収入を確保するには、複数のクライアントと信頼関係を築き、それぞれから継続案件を得られるようにするのが理想的です。
納期を守る、レスポンスを丁寧に返す、業務の質を安定させるなど、小さな積み重ねが次の依頼につながります。また1つの業種に絞らず、異なるジャンルの仕事も経験することで業界変化への耐性も高まるでしょう。幅広い仕事をこなしつつ、信頼を積み上げることが安定収入へのポイントです。
3.ポートフォリオや実績をこまめに更新する
在宅フリーランスにとって、ポートフォリオは自身のスキルや実績をアピールするための重要なツールです。新しい案件を受注するためには、持っている能力をクライアントにわかりやすく提示する必要があります。
そのためポートフォリオをこまめに更新し、最新の実績を反映させることが大切です。「〇〇の案件を経験しました」と記載するだけでなく、どのような課題を解決したのか、どのような成果が出たのかといった具体的な情報を添えると、より説得力の高いポートフォリオになるでしょう。
4.無理なく続けられる働き方を確立する
在宅フリーランスは働く時間や量を自分で決められる反面、がんばりすぎると体調を崩したり、精神的に疲弊したりする恐れがあります。健康を損ねてしまった場合、どんなにスキルがあっても仕事を続けることは難しくなるでしょう。自分にとって最適な作業時間や休憩の取り方を把握し、無理のないペースで働ける仕組みを整えることが大切です。
仕事ができる時間帯を明確に決めておく、休憩時間を設ける、プライベートの時間と仕事の時間を区別するなど、自分なりのルールをつくることで仕事と生活のバランスを保つことができます。仕事量が多すぎると感じた場合、ときには新しい案件を断る勇気も必要です。心と体の健康を第一に考え、長く続けられる働き方を見つけましょう。

未経験者が注意したい!在宅フリーランスが注意すべき4つのトラブルと対処法
在宅フリーランスとして働くうえで、未経験者が陥りやすいトラブルにはいくつかの共通点があります。代表的な例は、以下の4つです。
- 相場よりも極端に単価の低い案件は避ける
- 「初心者歓迎」という名の過重労働案件に注意
- 「とりあえず契約書なし」はトラブルのもと
- 修正依頼が無制限の案件には応じない
対処法も併せて解説します。
1.相場よりも極端に単価の低い案件は避ける
在宅フリーランスを始めたばかりの頃は、実績を積むために低単価の案件でも引き受けたくなる気持ちがあるかもしれません。しかし、相場よりも極端に単価の低い案件には注意しましょう。
作業内容が単価に見合わないほど多かったり、クライアントとのコミュニケーションがスムーズでなかったりなど、トラブルに発展するリスクが高いからです。スキルや労働の価値を不当に低く評価されないためにも、まずは業界の相場をしっかりリサーチして適正な単価の案件を選ぶようにしましょう。低単価の案件を無理に続けるよりも、適正な単価で質の高い仕事を一つずつ積み重ねるほうが、結果的に長期的なキャリアにつながります。
2.「初心者歓迎」という名の過重労働案件に注意
一見優しそうに見える「初心者歓迎」という言葉には、注意が必要です。なかには細かい指示が多く、膨大な作業量を強いられる案件も存在します。報酬が割に合わないまま、納期だけが厳しく設定されているケースも少なくありません。
さらに業務内容が曖昧な状態で作業を始めると、あとから追加依頼が重なることもあります。こうした案件に巻き込まれないためには、募集文を読み込むことが大切です。不明点がある場合は、契約前に必ず質問して確認しましょう。「初心者歓迎」の裏にある実情を見抜く目を持つことで、安心して業務に集中できる環境を選べるようになります。

3.「とりあえず契約書なし」はトラブルのもと
業務を開始する前に、契約内容を文書で取り交わしておくことは基本です。にもかかわらず、フリーランスの現場では「とりあえず始めましょう」と、契約書なしで作業に入ってしまうケースも少なくありません。
こうした状態でトラブルが起きた場合、報酬の未払いや修正回数のトラブル、納期の食い違いなどが発生しても自分を守る手段がなくなってしまいます。口頭やチャット上でのやり取りに頼るのではなく、納品物の範囲・報酬額・納期・修正対応などを明文化しておくことが大切です。書面契約が難しい場合でも、メールやメッセージの履歴を残すだけで証拠になります。小さな案件ほど、確認を怠らないようにしましょう。
4.修正依頼が無制限の案件には応じない
例えばWebデザインやライティングの案件は、納品後にクライアントから修正依頼を受けることが一般的です。しかし、なかには「修正は無制限」という条件を提示するクライアントもいるため注意が必要です。
修正回数に制限がないとクライアントの要望が際限なく続き、作業がいつまでも終わらないという事態に陥りかねません。修正作業も立派な業務の一部であり、自身の貴重な時間を消費するものです。そのため、事前に修正回数を「2回まで」や「初期提案の内容に関する軽微な修正は2回まで」などと具体的に定めておきましょう。契約時に修正範囲や追加料金が発生する条件について明確に合意しておくことで、トラブルを未然に防げます。
主婦(夫)必見!仕事と育児・家事との両立テクニック
在宅で働く主婦や主夫にとって、家事や育児と仕事のバランスをとることは大きな課題です。ここでは両立するためのポイントを5つ紹介します。
- タイムブロックで作業枠を先取りする
- 家族共有カレンダーで予定と締切を共有する
- 短時間でできる小タスクを組み合わせる
- 音声入力・スマホ作業を活用する
- ルーティン化と休憩設定で働きすぎを防ぐ
ぜひ取り入れてみてくださいね。
1.タイムブロックで作業枠を先取りする
タイムブロックとは1日のスケジュールを時間単位で区切り、あらかじめ仕事や家事、休憩などの時間を割り振っておく手法です。1日のなかで作業に使える時間をあらかじめ決めておくことで、仕事と家事を両立しやすくなります。
「何時までにこの記事を仕上げる」「何時から何時まではクライアントとの打ち合わせ」など具体的な作業内容と時間を事前に決めることで、気持ちの切り替えもしやすくなるでしょう。作業時間を視覚化することで集中力を高め、だらだらと仕事をしてしまうのを防ぐ効果も期待できます。
2.家族共有カレンダーで予定と締切を共有する
在宅フリーランスとして働く場合、家族の協力は不可欠です。仕事の納期や重要な打ち合わせの予定を家族と共有することで、理解と協力を得やすくなるでしょう。そこでおすすめなのが、家族共有カレンダーの活用です。
Googleカレンダーや共有可能な紙のカレンダーに、仕事の締め切りや打ち合わせの予定を書き込むだけでなく、子どもの学校行事や病院の予約、習い事の送迎など家族の予定をすべて一元管理しましょう。家族全員が互いの予定を把握でき「締め切り前だからこの時間は静かにしてほしい」といったお願いもしやすくなります。

3.短時間でできる小タスクを組み合わせる
在宅で仕事していると、子どもが突然泣き出してしまったり急な用事ができたりと、まとまった作業時間を確保するのが難しい場合もあるでしょう。そのようなときでも効率的に仕事を進めるために、短時間で完了できる小さなタスクをいくつか用意しておくのがおすすめです。
例えば「メールの返信」「リサーチ作業」「記事の構成を考える」など、15分や30分で終わる作業をリストアップしておきます。そして、スキマ時間ができたらすぐにそのタスクに取り掛かるようにするのです。これにより細切れの時間を有効活用でき、大きなタスクに取り掛かる準備も進められます。また、一つひとつのタスクを完了させるたびに達成感も得られ、モチベーション維持にもつながります。まとめて一気に仕上げようとするより、体力的にも精神的にも楽になるでしょう。
4.音声入力・スマホ作業を活用する
音声入力やスマホを活用した作業もおすすめです。例えば文章のアイデア出しや簡単なメールの返信は、音声入力機能を使えば手を使わず効率的に作業を進められます。またスマートフォンのアプリを使えば、簡単なデータ入力やSNS投稿、クライアントとのチャットでのやり取りなども場所を選ばずに進めることが可能です。子どもが寝ている間にパソコンに向かうのが難しい日でもツールを駆使することで、少しずつでも仕事を進められます。ただし音声入力は誤変換が多くなる可能性があるため、あとから必ず内容を確認するようにしてください。
5.ルーティン化と休憩設定で働きすぎを防ぐ
在宅で仕事していると、仕事とプライベートの境界線が曖昧になりがちです。つい働きすぎてしまい、疲労が蓄積してしまうケースも少なくありません。これを防ぐためには、仕事の開始時間や終了時間をルーティン化し、メリハリをつけることが大切です。
例えば「子どもを学校へ送り出したら、コーヒーを淹れてから仕事を開始する」といった自分なりのルーティンをつくってみましょう。ポモドーロ・テクニックのように「25分集中して作業し、5分休憩する」といったように、定期的に休憩時間を設定するのもおすすめです。休憩中には家事をしたりストレッチをしたりと、体を動かすようにするとよいでしょう。気持ちがリフレッシュでき、集中力を持続させる効果が期待できます。

扶養内で働く?収入・税金・社会保険ラインをわかりやすく整理
フリーランスとして働く場合、税金や社会保険の仕組みについても理解しておく必要があります。なぜなら、収入額によって受けられる控除や税額が変わってくるからです。ここでは、ポイントをわかりやすく解説します。
- 配偶者控除・配偶者特別控除ライン
- 健康保険扶養130万円/106万円基準の目安
- 所得税・住民税が発生するライン
- 確定申告が必要なケース
- 扶養を外れたあとの手続きと注意点
順番に見ていきましょう。なお、本内容は2025年8月時点の制度に基づいたものです。制度は変更の可能性があるため、常に最新の情報を確認しましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除ライン
給与収入が年間123万円以下であれば、配偶者(=控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合)に38万円の配偶者控除が適用されます。収入が123万円超〜160万円以下の場合は、配偶者特別控除が満額(配偶者控除と同額)となり、160万円超〜201.6万円以下では控除額が段階的に縮小します。給与収入が201.6万円を超えると配偶者特別控除は適用外になります。
なお、上記金額(123万・160万・201.6万)は給与収入ベースの目安です。フリーランスは「合計所得金額」で判定し、58万円以下=配偶者控除、58万円超〜133万円以下=配偶者特別控除、133万円超=対象外が原則です。合計所得金額は収入-必要経費等で算出し、青色申告特別控除や事業専従者の有無で変動します。
こうした控除は配偶者の合計所得金額に応じて緩やかに減額される仕組みで、2025年改正では控除額の水準自体は概ね据え置きの一方、判定基準(給与所得控除の最低保障額引上げ・配偶者の所得要件の見直し)が変更されています。なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用不可です。
年間収入が各ラインを上回る見込みがある場合、いつ・どの程度受注を増やすかを事前に計画し、税負担を無理なくコントロールしましょう。
健康保険扶養130万円/106万円基準の目安
健康保険の扶養判定は「今後12か月の見込みによる年収ベース」で見るのが基本です。フリーランスも年収見込で判定され、収入は総収入から事業に必要な経費等を差し引いた額を基準に認定されます(税務上の「事業所得」額と完全に一致するとは限りません)。おおむね年収130万円未満に加え、生計維持要件(被保険者の収入の1/2未満 等)を満たせば、配偶者の健康保険の扶養に入れるのが原則です。なお判定は見込み年収で行われるため、突発的な高収入があれば資格見直しに注意しましょう。
なお企業に雇用されている従業員のように、勤務時間が影響する「106万円の壁」は被用者向けの社会保険加入基準で、フリーランスには原則関係ありません。事業の立ち上げ期や副業レベルで働きたい人は、130万円ラインを意識しておくとよいでしょう。
所得税・住民税が発生するライン
基礎控除は一律48万円から段階制に変わり、合計所得132万円以下であれば95万円、655万円以下なら58万円というように所得帯ごとに控除額が設定されました。したがって最も控除額が大きい層では、総所得が95万円を超えると(他控除がなければ)所得税が発生します。
所得税は、基礎控除を含むすべての所得控除を差し引いた後の「課税所得」に課税される仕組みです。たとえば基礎控除95万円が適用され、他の控除がない場合は総所得が95万円を超えた時点で所得税が生じます。住民税の非課税ラインは、単身なら合計所得金額45万円以下で均等割・所得割とも非課税が一般的な目安です。給与のみの場合は年収100万円以下で所得割が非課税となる取り扱いが広く見られます(均等割は別判定、自治体により細部は異なる場合あり)。
経費や控除の計上次第で課税額が大きく変動するため「売上がいくらなら税金がいくら」という単純計算はできません。毎月帳簿を締め、現時点の所得を確認する習慣を持てば、年末に慌てずに済むでしょう。
確定申告が必要なケース
フリーランスとして継続的に報酬を得ている場合、各種控除後に所得税が発生する人は確定申告が必要です。申告要否は各種控除後に税額が生じるかで判断します(2025・2026年分は基礎控除が段階制で最大95万円)。扶養判定は別制度のため、申告要否には影響しません。
また事業所得として開業届を出している場合や、青色申告を申請している場合は、売上や経費を帳簿で記録し、正確に申告することが求められます。なお「年間20万円ルール」は、年末調整済みの給与がある人の副収入に限る所得税上の特例です。フリーランスが本業で給与がない場合には使えません。給与がある人でも20万円以下でも住民税の申告が必要な点に注意してください。
申告には白色申告と青色申告がありますが、白色申告でも帳簿作成は義務(単式簿記で可)です。帳簿付けが不安な人は、会計ソフトの導入を検討するとよいでしょう。

扶養を外れたあとの手続きと注意点
年間所得が基準を超えると扶養から外れ、自ら国民健康保険と国民年金に加入し直す必要があります。手続きは14日以内に市区町村役場で行うのが原則です。国民健康保険料は前年の所得等に連動する一方、国民年金保険料は定額(免除・猶予制度あり)です。したがって翌年度の国民健康保険料の負担が増える点に留意してください。
配偶者控除がなくなることで世帯全体の税額も上がるため、実際の手取りが思ったほど増えない場合もあります。扶養から外れる前に社会保険料や税金の増加分を試算し、キャッシュフローを確認しておきましょう。
経費計上と家事按分で税負担を抑える4つのポイント
在宅で働くフリーランスにとって、経費を正しく計上することは節税の第一歩です。ここでは、税負担を抑える4つのポイントを解説します。
- 在宅フリーランスで経費になる主な項目
- 光熱費・通信費の家事按分計算方法
- 自宅家賃・作業スペース按分の考え方
- 少額備品・10万円未満資産の処理
それぞれ見ていきましょう。
在宅フリーランスで経費になる主な項目
在宅フリーランスが事業のために支出した費用は、経費として計上可能です。主な項目には、以下が挙げられます。
- パソコン本体
- プリンター
- インターネット回線
- スマートフォン通信費
- 作業用ソフト
- 名刺作成費用
- 消耗品費(文房具など)
- 仕事関連の書籍代やセミナー受講料
- 外注費
これらの費用を漏れなく経費として計上することで所得を減らし、結果的に所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。日々の支出を記録するためにも、レシートや領収書は必ず保管しましょう。
光熱費・通信費の家事按分計算方法
在宅フリーランスの場合、電気代やインターネット料金も業務に使った分だけ経費にできます。これを「家事按分(かじあんぶん)」と呼び、事業と私用が混在する支出を合理的に分けて申告する方法です。例えば月にかかった電気代1万円のうち、平日9時〜17時の間を仕事に使っているなら、約30〜40%程度を経費にできるケースが一般的です。
通信費も同様に業務用メールや打ち合わせ、調査などで使用している割合を目安に按分できます。税務署に説明が必要な場合に備えて、使用時間や用途の記録を残しておくと安心です。相場感や税理士のアドバイスも参考にしながら、無理のない比率を設定しましょう。
自宅家賃・作業スペース按分の考え方
自宅の一部を仕事場として使っている場合、家賃の一部も経費として認められます。例えば家全体が60㎡で、そのうち6㎡の部屋を仕事専用に使っていれば、全体の10%が経費対象です。
ただし寝室やリビングの一角などを仕事に使っている場合は、明確に「仕事のためのスペース」であることが条件です。机や資料棚だけで構成されたコーナーでも構いませんが、プライベートとの境界があいまいな場合は按分率を低めに設定しておくとよいでしょう。
少額備品・10万円未満資産の処理
購入価格が10万円未満の備品は、減価償却せずにその年の経費として一括計上できます。一方で10万円以上の備品は「減価償却資産」となり、原則として数年にわたって少しずつ経費として計上していく必要があります。
ただし青色申告している場合は「少額減価償却資産の特例」を利用することで、30万円未満の資産なら、その年に全額を経費に計上可能です。特例を活用することで購入した備品の費用を一度に経費にでき、節税効果を高められます。
インボイス制度と請求書対応の基本
2023年10月から始まったインボイス制度は、フリーランスとして働く人にとって取引に大きな影響を与える制度です。ここでは、基本を解説します。
- インボイス制度の基礎用語と仕組み
- 登録が必要か判断する収入・取引条件
- 適格請求書発行事業者登録の手続き手順
- 免税事業者のまま取引する場合の注意点
- 発注先とのインボイス交渉フレーズ例
ポイントを理解しておきましょう。
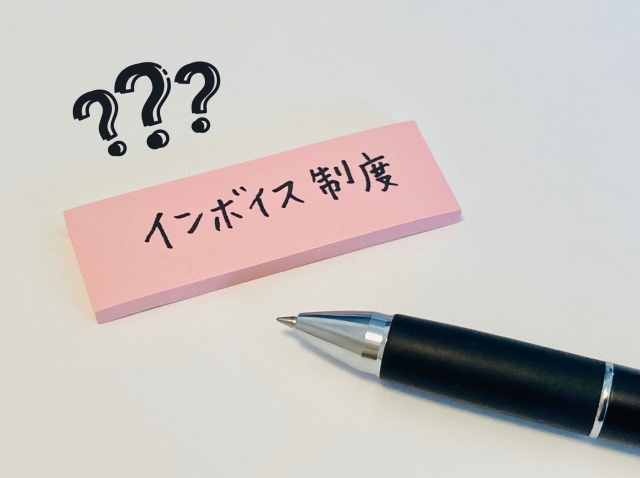
インボイス制度の基礎用語と仕組み
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)を発行できる事業者だけが、取引先に対して仕入税額控除の対象となる請求書を出せる仕組みです。消費税を支払っている企業や個人が、他の事業者から仕入れる際に「仕入税額控除(支払った消費税を差し引ける制度)」を受けるためには、登録された相手からの請求書が必要になります。この登録を受けた人を「適格請求書発行事業者」と呼びます。
課税事業者が消費税の納税額を計算する際に、インボイスとして認められない請求書からの仕入れについては、原則として消費税分の控除が受けられません。(ただし経過措置により、免税事業者からの仕入れでも2023年10月1〜2026年9月30は80%、2026年10月1〜2029年9月30は50%まで控除可)
これにより発注元の企業や事業者は、インボイスを発行できる事業者との取引を優先するようになる可能性があるため、フリーランスも対応を検討する必要があります。
登録が必要か判断する収入・取引条件
「年間の課税売上が1,000万円を超えたら登録必須」というルールではありません。登録そのものは任意ですが、仕入税額控除に対応する請求書を発行するには登録が必要です。基準期間の課税売上が1,000万円超の事業者は消費税の課税事業者となるため、実務上は登録が前提になりやすい一方、BtoC中心なら登録しなくても影響が小さいケースもあります。要は「取引先が仕入税額控除を必要としているか」で判断しましょう。
適格請求書発行事業者登録の手続き手順
インボイス制度に対応するためには、国税庁に「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。申請はe-Tax(電子申告)または書面で可能です。登録できるのは課税事業者に限られます(登録すると登録日以降、適格請求書の交付義務が生じる)。
免税事業者が登録する場合は原則「課税事業者選択届出書」が必要ですが、2029年9月30日までの経過措置では、登録申請だけで課税事業者となれる特例があります。なお「開業届」は事業開始の届出であり、インボイス登録の法的な前提要件ではありません。
登録が完了すると「T+13桁」の登録番号が発行され、請求書等に記載します。請求書作成ソフトやクラウド会計を使えば、フォーマットを自動で対応させることもできるため、実務負担を軽減できるでしょう。
免税事業者のまま取引する場合の注意点
インボイス制度への登録は任意のため、免税事業者のままで働き続けることも可能です。しかし取引先が課税事業者の場合、免税事業者であるあなたに支払った消費税分を原則控除できない(上記の経過措置で一部控除は可)ため、取引条件の見直しや値下げを求められる可能性があります。
値下げ要請の方法次第では下請法・独占禁止法上の問題になり得るため、事前の説明・協議の記録化を意識しましょう。
発注先とのインボイス交渉フレーズ例
インボイス対応の可否を取引先に確認する際は、柔らかい表現を使いながらも事実を明確に伝えることが大切です。例えば「現在は免税事業者のため、適格請求書の発行はできませんが、御社のご方針に応じて対応を検討いたします」などと伝えれば、相手に選択の余地を残した形になります。
登録予定がある場合は「申請中であり、登録番号が発行され次第ご案内いたします」といった前向きな文言を添えると安心感を与えられるでしょう。請求書のテンプレートに関しても「インボイス対応・非対応」の両パターンを用意しておくと、柔軟に対応しやすくなります。言葉選び一つで信頼性が変わるため、丁寧な説明を心がけましょう。
まとめ
在宅フリーランスという働き方は、自由度の高さやライフスタイルに合わせやすい点で多くの魅力があります。未経験からでも始められる仕事は数多くあり、学びと工夫次第で長く安定して働くことも可能です。ポイントを押さえて、自分らしい働き方を見つけてみてくださいね。
同時に収入管理や税務対応など、個人で担うべき責任についても考えていかなければなりません。特に税金や扶養の知識、インボイス制度への対応などは、フリーランスとして継続していくうえで避けて通れないテーマです。正しい知識を身に付けて計画的に行動することで、予期せぬトラブルや損失を防げます。







