個人事業主とフリーランス・自営業との違いは?手続きや補助金など基本も徹底解説

働き方の多様化が進む現代社会では、会社員ではなく個人事業主やフリーランスという道を検討する人が増えています。「個人事業主になりたいけど、フリーランスや自営業との違いがよくわからない…」「それぞれに必要な手続きや利用できる補助金が違うの?」と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、個人事業主の基本を徹底解説します。必要な手続きをはじめメリット・デメリット、インボイスや補助金についてまとめているので、これから個人事業主になりたいと考えている人は参考にしてください。
個人事業主とは?フリーランスや自営業との違いも解説
「自分で事業を始めたいけれど、個人事業主とフリーランス、自営業の線引きがわかりにくい」と感じている人もいるでしょう。ここでは、違いを解説します。
- 個人事業主は個人で事業を営む人を指す
- フリーランスとの違い
- 自営業との違い
それぞれ見ていきましょう
個人事業主は個人で事業を営む人を指す
個人事業主とは、税務署に開業届を提出して事業所得を得ている人を指します。税法上の区分であり、働き方や職種を限定するものではありません。例えば会社員が副業でネットショップを運営している場合や、定年退職後に趣味の陶芸教室を開いている場合も、開業届を提出すれば個人事業主となります。
業種はさまざまで、例えば飲食店を経営するオーナーシェフ、町の電気店や八百屋の店主、web制作を行うデザイナーやプログラマー、フリーのWebライターやカメラマンなども個人事業主に該当します。いわゆる「一国一城の主」として独立して事業を営んでいる人たちが、個人事業主です。
なお、一時的に不用品をネットオークションやフリマアプリなどで販売するだけでは、個人事業主とはいえません。

フリーランスとの違い
フリーランスは、個人事業主や法人などといったような税法的な区分を示す言葉ではなく、特定の会社、団体を通さずに働くスタイルを指します。働き方そのものを示すので、なるにあたって必要な手続きは特にありません。単なる呼び方、呼称といってもよいでしょう。
自営業との違い
自営業とは自分自身で事業を営んでいる人や、その働き方のことを指します。つまり企業に雇われず、自分の判断で仕事をして収入を得ている人たちのことです。
業務形態を見ると、自営業は店舗を構えた商売や家族経営の事業など比較的従来型のビジネスモデルを指すことが多いです。例えば個人商店の店主、町の工務店の経営者、農業を営む農家などが挙げられます。こうした事業を個人名義で行っている場合は個人事業主であり、同時に自営業者でもあるということになります。
一方でプログラマーやイラストレーターなど、企業に所属せず依頼された仕事をこなして報酬を得るといったスタイルで働く人が、フリーランスと呼ばれることが多いです。明確な違いはありませんが、場所や時間が決まっていて一定の決まったサービスを提供していれば自営業、都度仕事を請負い、自宅などで仕上げたものを納品して報酬を得るといった場合がフリーランスと呼ばれることが多いといえます。
個人事業主は誰でもなれる?
事業を行う者であれば、開業届を出すことにより個人事業主になれます。主婦はもちろん、会社員が副業の一貫として、または学生や法人の経営者も個人事業主になることが可能です。
とはいえ、企業と雇用契約を結んで働いている会社員は、就業規則で副業に関して規定が盛り込まれていたり、禁止されているケースがあるので注意しましょう。
副業が法律で禁止されていることはありませんし、むしろ近年は副業を後押ししている傾向がありますが、本業に不利益を与えることを避けるため、副業は事前申告制にしている企業も多いのです。なお、子育てのために仕事を辞めた専業主婦が、個人事業主になるケースも増えています。
過去の経験を活かし経理や人事業務に従事したり、Webデザインやプログラミングなど新たなスキルを習得し仕事を受注していくなど、そのスタイルはさまざまです。現在は政府の推し進めるICTの恩恵もあり、今後ますますチャンスは拡大すると推測されます。
個人事業主になるために必要な手続き
個人事業主になるためには、管轄の税務署で個人事業主としての開業届を提出しなければなりません。書類は、国税庁のホームページからダウンロード可能です。個人事業主の届出は、直接税務署に提出する方法と郵送で提出する2つの方法があります。
税務署に提出する書類の名称は「個人事業の開廃業届出書」と言い、原則として開業から1か月以内に納税地の税務署へ提出しなければなりません。
他にも「freee開業」というオンラインソフトを利用すれば、無料で簡単に開業届を作成できます。お金をかけずに正確な開業届を作成したい場合は、クラウドソフトを利用するとよいでしょう。

個人事業主になったあとにするべき4つのこと
個人事業主になったあとは、するべきことがいくつかあります。Webデザインやアプリ開発、ライティングなどの作業だけでなく、企業にいたら別の担当者がやっていてくれたような庶務や営業行為もしなくてはならないためです。ざっくりとまとめると以下のような表になります。
それぞれの作業について説明していきます。
1.届出
個人事業主になる場合、税務署に「開業届」の提出が必要です。基本的には、個人事業主になってから1か月以内に出すこととされています。提出が遅くなっても特に罰則はありませんが、青色申告したい場合は提出必須なので忘れないようにしましょう。
また個人事業主の場合、青色申告により大幅に節税をすることができます。したがって、どうしても白色申告で済ませたいという人以外は、青色申告承認申請書も合わせて出すのがおすすめです。なお、配偶者や親族に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出」も提出する必要があります。
その他の従業員を雇用する場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を出したうえで「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も併せて提出するとよいでしょう。
2.社会保険
会社員の場合、国民健康保険や年金の保険料は毎月の給与から天引きされています。つまり本人は意識していなくても、企業が代わりにきちんと納めていてくれているということです。しかし個人事業主の場合、自分自身で納付する必要があります。
また、会社員で厚生年金に加入していた場合、保険料の半分を企業が分担してくれていますが、個人事業主の場合は自分自身が国民健康保険料の全額を負担することになります。
3.事務・営業
例えば企業で働いている場合、契約は営業が、作業をエンジニアが、経理作業は経理担当が分担して行っているといったスタイルが一般的です。しかし個人事業主の場合、基本的に自分ですべてを行わなければならず、特に仕事を獲得するための営業活動は欠かせない作業となります。
4.経理
個人事業主の場合、1年に1度、自分自身で確定申告する必要があります。白色申告にせよ、青色申告にせよ、日々の取引の帳簿を付けるのは必須作業です。また売上げを請求するために、請求書の発行や入金の確認も必要です。もちろん収支が赤字でないか、出金や売上げの把握も日々必要といえるでしょう。
個人事業主になる4つのメリット
個人事業主になる主なメリットは、主に4つあります。
- 自分の好きなことや得意なことを仕事にできる
- がんばり次第で稼げる
- 法人と比べて手続きが簡単
- 働き方の自由度が高い
それぞれ解説します。
1.自分の好きなことや得意なことを仕事にできる
個人事業主は、事業内容を自由に決められます。つまり、自分の好きなことや得意なことを仕事にできるのです。「趣味や特技を活かして仕事をしたい。」「自分のアイデアを形にしたい。」と考えている人にとって、個人事業主は魅力的な働き方といえるでしょう。
例えばイラスト制作が得意な人なら、イラストレーターとして活動できます。プログラミングスキルを持っているなら、システム開発やWebサイト制作を仕事にできるでしょう。自分で仕事内容を決められるため、モチベーションを維持しながら働くことができます。仕事に対する満足度も高くなるでしょう。

2.がんばり次第で稼げる
個人事業主は、会社員のように給与が決まっているわけではありません。そのため、がんばり次第で収入を増やせる可能性があります。例えば一般的なフリーランスエンジニアの場合、スキルや経験によっては時給5,000円以上の単価設定も可能です。月に160時間働けば、単純計算で月収80万円となります。
あくまでも一例で業種や専門性によって単価は大きく変動しますが、努力次第で収入を増やせる点は会社員にはない魅力といえるでしょう。
3.法人と比べて手続きが簡単
個人事業主は、法人と比べて設立や運営の手続きが簡単です。法人を設立する場合は定款の作成や登記申請など、複雑な手続きをしなければなりません。個人事業主なら、税務署に開業届を提出するだけで事業を開始できます。
また税務処理も、法人と比べて簡単です。法人は、複雑な会計処理や税務申告をしなければなりませんが、個人事業主は比較的簡単な帳簿付けと確定申告だけで済みます。
4.働き方の自由度が高い
働き方の自由度が高いことも、大きなメリットです。企業勤めをしていると勤務時間や場所が指定されるケースが多く、柔軟に動きづらい部分もあるでしょう。個人事業主は、仕事内容だけでなく働く時間帯、仕事場所なども比較的自由に決められます。
例えば、早朝の集中力が高い時間帯に仕事して午後は自由時間に充てたり、夜型であれば深夜に作業したりも可能です。またリモートワークを基本とすれば、カフェやコワーキングスペース、ときには旅行先のホテルなど、場所を選ばずに働けます。自己管理能力や時間管理スキルは求められますが、そのぶん得られる自由度は大きいといえるでしょう。
個人事業主になる3つのデメリット
メリットばかりではありません。個人事業主になる主なメリットは、次の3つです。
- 収入が不安定
- 社会保険や福利厚生が薄い
- 社会的信用度が低い
それぞれ解説します。
収入が不安定
個人事業主は、会社員のように毎月決まった給与が保証されているわけではありません。収入が不安定になりやすい点は、デメリットです。「今月はたくさん稼げたけど、来月はどうなるかわからない。」「収入が安定しないから、将来が不安。」と、感じながら働く人も多くいます。業種や時期、景気の変動に大きく左右されるため、案件が立て込む月もあれば思うように仕事が取れない月もあるのです。
特に開業初期には固定の取引先が少なく、集客や営業活動に苦戦するケースも多く見られます。また収入が減っても、有給休暇や傷病手当などの補填制度は基本的に存在しません。安定した収入を得るには、長期的な視野での計画と経営的な視点を持つ必要があります。事業用口座を分けて資金管理を行い、緊急時に備えて生活費を数か月分貯蓄しておくなどの備えをしておくとよいでしょう。
社会保険や福利厚生が薄い
個人事業主は、会社員のように社会保険や福利厚生が充実していません。例えば会社員は、健康保険や厚生年金に加入していますが、個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。国民健康保険と国民年金は、会社員が加入する健康保険や厚生年金に比べて、保障内容が薄いのが現状です。
また会社員は、企業から住宅手当や家族手当などの福利厚生を受けられるケースも多いですが、個人事業主には、基本的にありません。そのため、自分で将来に備えて貯蓄や保険に加入する必要があります。
社会的信用度が低い
社会的な信用度が、会社員よりも低く見られがちな点もデメリットです。例えば住宅ローンや自動車ローンの審査においては、収入の安定性が低いと判断されて審査が厳しくなる傾向にあります。
実際に「希望の住宅ローンが通らなかった」「クレジットカードの審査で落とされた」という事例もあります。特に開業して間もない場合は、過去の実績や収入証明を求められることが多く、提示できないと信用が得られにくいのです。
また取引先との関係においても、法人と比較すると規模の小ささが不安視され、契約をためらわれるケースも見受けられます。こうした信用のハードルを越えるには、確定申告書や納税証明書などを用意し、継続的に事業運営していることを証明していく努力が必要です。
インボイスに登録するべきか?メリット・デメリットを解説
2023年10月からインボイス制度が導入されました。「登録しないと取引に支障が出るのでは?」「登録したら消費税の負担が増えるかも」と迷う人が多くいます。ここでは、インボイス制度に登録しない場合のメリット・デメリットについて見ていきましょう。
- 登録しないメリット
- 登録しないデメリット
- 影響を受けにくい事業者
それぞれ解説します。

登録しないメリット
インボイス制度に登録しない最大のメリットは、消費税の納税義務が免除されることです。インボイス制度に登録すると課税事業者となり、消費税の申告と納税が必要になります。しかし登録しなければ今まで通り免税事業者として活動できるため、年間売上が1,000万円以下であれば消費税を納める必要がありません。
また、インボイス制度に対応した請求書発行システムを導入したり、経理処理を変更したりする必要がないため、事務処理の負担を軽減できます。特に1人で業務をこなしている事業主にとって大きな利点といえるでしょう。
登録しないデメリット
インボイスに登録しないことで得られる「免税」という立場にはリスクも潜んでいます。特にBtoB(企業間取引)を中心にしている場合、取引先が仕入税額控除を受けられなくなることから「インボイス発行ができないなら契約を継続できない」と判断されるケースが増えているのです。
例えば消費税10%が課される取引において、取引先が税額控除を受けられないとなると、実質的にその負担を取引先が背負うことになります。そのため登録していない事業者との契約を見直したり、値引き交渉を求められたりする可能性が高くなります。つまり短期的には得に見える選択でも、長期的な事業継続や取引安定性の観点からは慎重な判断が求められるのです。
影響を受けにくい事業者
インボイス制度の影響を受けにくいのは、主に消費者向けビジネス(BtoC)を展開している事業者です。例えば、美容師・整体師・小売業者・学習塾などが該当します。これらの業種では取引の相手が一般消費者であることが多く、仕入税額控除の必要性がありません。
また電子書籍やデジタルコンテンツの販売など、プラットフォームを介して個人向けに販売しているクリエイターも、インボイスの影響は限定的です。登録していなくても、売上や信頼性に大きな影響が出ることは少ないといえます。
ただし「将来的に取引先の幅を広げたい」「法人との契約を増やしたい」と考えている場合は、将来的な登録を視野に入れておくことが望ましいでしょう。
【2025最新】個人事業主が受けられる主な補助金3つ
個人事業主に挑戦したいけれど、資金がないと悩む人もいるでしょう。ここでは、個人事業主が受けられる主な補助金を3つ紹介します。
- IT導入補助金
- ものづくり補助金
- 事業再構築補助金
それぞれ見ていきましょう。
1.IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が業務効率化や売上アップのためにITツールを導入する費用を一部補助する制度です。例えば会計ソフトや受発注ソフト、ECサイト構築など、業務のデジタル化を促進するさまざまなツールが対象となります。
補助額は導入するITツールや類型によって異なり、5万円から450万円まで幅広く設定されています。IT導入支援事業者と呼ばれる専門家が、ツールの選定から申請手続きまでサポートしてくれるので、ITに詳しくない人でも安心して申請できます。
2.ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が革新的な製品やサービスの開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資などを支援する制度です。具体的には、新しい機械の導入やシステムの構築などが対象となります。
技術力の向上や生産性革命を目指す事業者を支援することを目的としており、補助上限額は事業内容や類型によって異なります。申請には、自社の技術やアイデアを具体的に説明する事業計画書の作成が必要です。
3.事業再構築補助金
事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症の影響や経済社会の変化に対応するため、中小企業などが思い切った事業の再構築に挑戦することを支援する制度です。具体的には、新分野展開・事業転換・事業再編などの取り組みを支援し、事業者が新たな成長分野へ進出することを後押しします。
補助対象となるのは中小企業(個人事業主も含まれる)や中堅企業などで、認定経営革新等支援機関から事業計画書の確認を受けることが必須要件です。補助金額は事業規模や従業員数などによって異なり、公募によって選ばれた事業者が支援を受けられます。

売り上げが増えたら個人事業主ではなく法人化するべきか
個人事業主として事業を始めた人のなかには「このまま個人事業主でいいのだろうか」と悩む人も少なくありません。事業規模が拡大するにつれて、個人事業主としての限界を感じることもあるでしょう。法人化は大きな決断です。そこで、法人化のタイミングやメリットについて解説します。
目安は年間所得が800万円を超えたら
一般的に、年間所得が800万円を超えたら法人化を真剣に考えるべきタイミングだといわれています。なぜ800万円が目安となるのでしょうか。これには、個人事業主と法人の税負担の違いが関係しています。
個人事業主の場合は、累進課税が適用されます。つまり、所得が増えるほど税率が上がっていくのです。一方で法人の場合は、所得が増えても税率は変わりません。
例えば個人事業主の場合、所得が1,000万円を超えると最高税率の45%が適用されます(2025年現在)。これに対し、法人税率は原則として23.2%です。さらに中小企業向けの軽減税率を適用すると、年800万円以下の所得部分については15%の税率が適用されます。
そのため、年間所得が800万円を大きく超える場合は法人化したほうが税負担を抑えられることが多いのです。ただし、あくまで目安であり、事業内容や経費の状況によって最適な判断は異なります。税理士などの専門家に相談し、自身の事業に合った選択をすることが重要です。
法人化するメリット
法人化によって得られるメリットは、税制面の優遇だけではありません。例えば役員報酬を自分に支払うことで、所得を分散させつつ経費として計上できるため、節税が可能になります。
また、社会的信用が高まる点も大きなメリットです。法人として登記することで、個人名ではなく会社名で取引できるようになります。取引先や金融機関からの信用度が向上し、新たなビジネスチャンスに繋がる可能性もあるでしょう。
個人事業主は必ず確定申告が必要?4つのポイントを解説
個人事業主として活動するなら、忘れてはいけないのが確定申告です。ここでは、4つのポイントを解説します。
- 一定の所得額を超えたら必要
- おすすめは青色申告
- 青色申告の場合は複式簿記による帳簿付けが必要
- 経費や社会保険料を計上して節税しよう
それぞれ見ていきましょう。
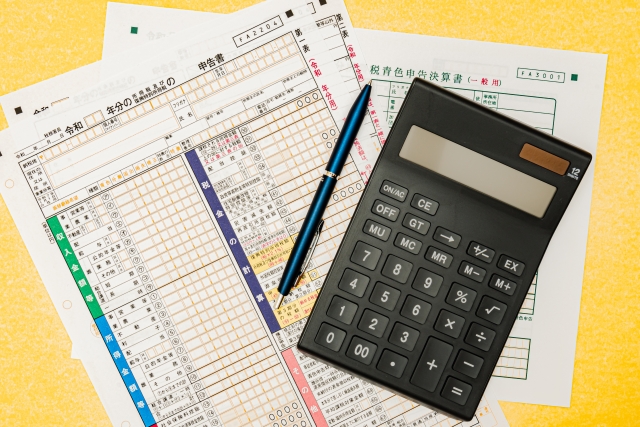
1.一定の所得額を超えたら必要
個人事業主になったら、届出の有無に関わらず所得48万円以上ある場合は確定申告する義務が発生します。売上から経費を差し引いたあとの所得が、年間48万円以下の場合は確定申告する必要はありません。
ただし、この場合もあとで税務署から調査される可能性がありますので必ず経費のレシートや帳簿を保管しておくことが重要です。確定申告には、白色申告と青色申告の2種類がありますが、控除額が大きいのは青色申告のほうです。青色申告で確定申告するためには、事前に税務署への必要書類の提出が必要となります。
一定の所得額があるにもかかわらず確定申告をしていないことが発覚すると、延滞税や無申告加算税のような高額の追徴課税が課されることになりますので注意しましょう。
なお、個人事業主ではなく会社員が副業で収入を得た場合は、年間所得20万円までが上限となります。混同しないようにしましょう。
2.おすすめは青色申告
おすすめなのは、青色申告です。白色申告は単式帳簿(お小遣い程度の内容)の提出で済み、事前の届け出も必要ありませんが特別な控除がありません。
例えば売上300万円、経費80万円、社会保険料50万円の個人事業主がいたとしましょう。
白色申告の場合は
300万円-80万円-50万円=170万円(所得)
170万円×5%(195万円以下の税率)=85000円(所得税)
一方、青色申告の場合は最大65万円までの特別控除を受けられるので、
300万円-80万円-50万円-65万円(特別控除)=105万円
105万円×5%=52500円(所得税)
となり、32500円所得税額が異なります。
上記の例では所得がそれほど大きくないため、税金の差額が少ないように感じられますが、所得税は所得が増えるごとに税率が上がる仕組みになっていますので、所得が多い人ほど納める税金の額も増えるのです。
上記の例では、年間所得195万円以下のカテゴリーで所得税率は5%でしたが、年間所得195万円以上のカテゴリーでは、10%、15%と徐々に税率が上がっていきます。
年間所得が195万円と196万円の境目だったとしたら、経費と特別控除を使って195万円以下にするほうが、納める税金は少なくて済みます。青色申告がいかに節税効果の高い方法か、おわかりいただけたのではないでしょうか?
3.青色申告の場合は複式簿記による帳簿付けが必要
個人事業主が青色申告するためには、複式簿記による帳簿の作成が必要です。事業の売上といった収入と、備品の購入や家賃といった支出を、それぞれ借り方と貸方の両方に分けて記入していかなければなりません。
また、記入する内容によって勘定科目というのが決められており、同じ経費でも書籍と交通費では記入すべき科目が異なります。細かい仕分け作業と帳簿への記入は、経理の知識がない人にとっては、なかなか骨の折れる作業です。
確定申告は年1回ですが、帳簿の作成はこまめにしておかないと、レシートや請求書がどこにいったのかさえわからなくなり、経費として計上ができない事態にもなりかねません。
おすすめは、クラウド会計ソフトの「freee」などを利用して、簡単に帳簿を作成する方法です。月額980円程度から利用でき、事業用の口座やクレジットカードを登録しておけば、自動で会計ソフト上に経費を仕分けして記入してくれる優れものです。
また、確定申告書類を作成する機能もついているので、確定申告をしたことがない人でも、簡単な質問にソフトウェア上で答えるだけで、書類を作成できるのです。税理士に書類作成をお願いすると、確定申告のみで15万円ほどかかります。クラウド会計ソフトで税務処理すれば年1万2000円ほどで済むため、検討してはいかがでしょうか。
4.経費や社会保険料を計上して節税しよう
確定申告する場合は、売上から経費や社会保険料などの各種控除を差し引くことができます。
所得=売上-経費-各種控除
所得×税率=所得税
経費として計上できるものは、いろいろありますが、例えばネットショップの運営で物販を行っている方を例にとると
- ネットショップの出店料
- 商品の仕入れ代金
- インターネット回線の利用料
- 商品を保管している倉庫の代金
- 発送料
- 梱包費用
などのようなものを経費として計上できます。経費として使ったものについては、必ずレシートや領収書を保管し、記録を残しておく必要があります。また、パソコンや車のような高額の設備投資をした場合は固定資産として固定資産台帳に登録し、減価償却という形で経費に計上します。
個人事業主におすすめの職種10選
「個人事業主になりたいけど、どの職種で活動していくか迷う」という人もいるでしょう。ここでは、おすすめの職種を10種紹介します。
- Webデザイナー
- コーダー
- プログラマー
- イラストレーター
- ライター
- データ入力
- カスタマーサポート
- コールスタッフ
- オフィスサポート(経理・人事・労務)
- 翻訳
それぞれの特徴を解説します。
1.Webデザイナー
Webデザイナーとは、Webサイトのデザインを行う職業です。「どのようなサイトにするのか」から始まり、トップページを含めた各ページの配置、画面構成、色使いやフォントデザインなど、Webサイト全般を企画していきます。
主に社内のWebサイトのみを取り扱うインハウスタイプと、さまざまな企業からWebデザインを請け負うデザイン会社勤務とにわかれていますが、最近ではフリーランスで請け負う人が増えています。
その場合、よほど実績があったり宣伝力があったりする人以外は、どこかのデザイン会社から業務委託という形で受けるのが一般的といえます。その場合、1件当たりいくらという報酬額が提示されているケースと、時給換算で紹介されている場合とがあります。
基本的には、クライアントからの依頼に基づき進めていく仕事なので、相手のニーズをうまく聞き出す力、IT関連の専門知識、相手に説明し納得させることができるプレゼン力が求められます。
ママワークスでお仕事を探す
2.コーダー
コーダーとは、Webデザイナーの指示に基づき実際にサイトを構築する職業です。1つの企業のサイトを数ページにわたり作る場合や、ランディングページだけを作って納品していくケースがあります。
htmlやCSS、JavaScriptといった言語を用いて作成するのですが、比較的初心者でも習得しやすいということもあり、これからフリーランスとして活躍していきたいという主婦の人に人気の職種でもあります。
フリーランスの場合、勤務時間が決められているわけではなく、納品日までに仕上げれば良いというスタイルも人気の理由です。子育てしながら、または会社員が副業として始めるケースも増えています。
ママワークスでお仕事を探す
3.プログラマー
プログラマーとは、各プログラミング言語を用いてさまざまなプログラム、アプリケーションを作り上げる職業です。銀行のATM、工場などの機械、パソコン上のソフト、スマホのアプリ、オンラインゲームなど、これらすべてがプログラミングで成り立っています。
専門性が強く、スキルを持っていれば転職しやすい点もプログラマーの特徴です。実際に働く環境等の理由で、より働きやすいところでリスタートを切るという人も多いです。
また独立してフリーのプログラマーとしての道を歩んだり、起業する人も少なくありません。第一線で働くプログラマーであれば、年収1,000万を超えることもあります。
とはいえ、ツテがあり仕事に事欠かないという人でなければ、最初はプログラマーに案件を紹介してくれるエージェントに登録するか、クラウドソーシングサイトや求人情報サイトで仕事を探すのがおすすめです。
なお、子育てが一段落したママや、会社員が副業としてプログラマーを目指す場合、プログラミングを学ぶことができるオンラインスクールを活用するのがおすすめです。最初は簡単な案件しかこなせなくても、スキルアップしていけば高額な報酬を得られるようになるでしょう。
ママワークスでお仕事を探す
4.イラストレーター
イラストレーターとは、キャラクターや風景などのイラストを描く職業です。現在求められている多くの案件が、デジタルのイラスト画を納品する仕事となっています。活躍範囲は広く、それぞれの得意分野を活かせる仕事といえるでしょう。
例えば人物一つとっても、ゲームやアニメーションで使用されるキャラクターのイラストや、実在する人物の似顔絵イラストなのかでも違いますし、人物以外でもWebサイトや営業資料、パンフレット等に使用する説明用イラスト、製品パッケージやチラシなどに使用するイラスト、パンフレットなどに載せる地図イラストなど、ありとあらゆる場面にニーズがあるためです。
なお、基本的にはIllustrator®やPhotoshop®といった描画ソフトを使いこなすスキルが必要です。と同時に、どのようなイラストが求められているか的確にとらえる力、プレゼン力も実は同じくらい求められているといえます。なぜならイラストは、目的があってその創作が必要とされるためです。
営業資料に使用するようなイラストであれば、文字による説明とともに、そのイラストを見れば、見る側がすんなりと内容を理解できるといったような表現がなされている必要があります。いくらデザイン性が高くても相手に伝わらないのでは、イラストレーターとしては評価されない可能性が高いです。
楽器を持ったキャラクターを描くのであれば、楽器に詳しくなくても、その楽器を正しく表現しなければならないときも出てきます。そのときに、実際に実物を見たり、資料を手に入れたりするなどして、相手が求められるレベルで表現していくことが必要となります。
イラストレーターは、さまざまな職業のなかでもフリーランスが多い傾向にあり、これから個人事業主としてイラストを作成する仕事をしたいという人にとって、比較的進みやすい道といえるでしょう。いっぽうで、多くのフリーランスがすでに存在するため、いかに仕事を受注し、安定した収入を得られるかがポイントとなります。
クラウドソーシングサイトを通じて仕事を受注する努力はもちろん、ポートフォリオの作成、SNSを使ったPRなど、徹底した自己プロデュースが大切です。
ママワークスでお仕事を探す

5.ライター
ライターとは、本や雑誌などのメディアの記事を制作する職業です。最近では、Webサイト上で読まれるWebメディアが増えており、ニーズもWebライターも増加傾向にあります。
誌面のライターと同様、正しい日本語を使うこと、事実を書くこと、情報もとを明らかにすること、他の人の記事を盗用しないことは当然ですが、Webメディアライターに求められこととして、検索上位になるよう記事を制作するスキルが挙げられます。
検索エンジンでキーワード検索したときに上位になるほうがクリックしてもらえる確率があがることから、いかに上位に表示される記事にするかが重要になるためです。
いわゆるSEOライティングと呼ばれるものですが、世界で圧倒的なシェアを誇るGoogle検索に対応して記事を書くことを指します。とはいえ、未経験者向けの仕事もたくさんあります。
そもそもライターには資格は不要であり、Web記事や新聞、書籍などから情報を集め、それを自分なりの言葉でまとめて記事を書くといったことができれば、十分お仕事を受けられるといえます。なお、当然コピペは厳禁です。他のサイトと酷似していると通らないことがあります。チェックツールもあるので、うまく活用しながら案件をこなしていくとよいでしょう。
1文字あたり○円といった形での契約となり、記事が仕上がって納品したら報酬がもらえるといった仕組みとなっています。慣れてくると1本あたりにかける時間を短くできるので、まずは数を書くといった気持ちではじめてみるとよいでしょう。
ママワークスでお仕事を探す
6.データ入力
「子育てしながら在宅ワークをしたい」というママに特に人気の仕事がデータ入力です。在宅ワーク初心者でも、パソコンの基礎知識があれば比較的誰でも挑戦できるためです。
基本的には企業から依頼されたデータを入力していきますが、タイピングが可能であれば特別なスキルを求められることはありません。ただし、集計や正確なデータ入力等を目的として関数の知識が条件とされている場合はあります。
データ入力の報酬は、1件あたり○円、もしくは1つの仕事あたり○円といった形で決められていることがほとんどです。作業時間が決められているのではなく、納品日までに仕上げるといった形式がほとんどなので、お子さんがお昼寝している間に少しだけやりたいといった方に向いた仕事といえます。
なお、なかには文字起こしという案件もあります。会議やシンポジウムなどの音声を聞いて、それを文字にするといったものです。これは簡単そうで、慣れるのに意外と時間がかかると言われていますので経験者向けです。
一方で、オークションやフリマサイト、ECサイトへの商品登録といった仕事もあります。Excelは不得意でも、出品経験があるなどといった場合は、そちらもおすすめです。
ただし、なかには高額なブランド品出品のお手伝いということで、偽ブランドの取り扱いをさせられ犯罪の一望を担がされたり、買い取り式になっていてお金をだまし取られたりといったトラブルも散見されます。
高額報酬につられて、安易にインターネットやSNSなどで請け負うということは避け、信頼のおける求人情報サイトやクラウドソーシングサイトを活用して仕事を探すことがおすすめです。
ママワークスでお仕事を探す
7.カスタマーサポート
お客様からのお問い合わせに対応するのがカスタマーサポートという職業です。最近では、自宅にいながらにして受電するという案件が増えています。
パソコンやヘッドセットなどの準備が必要ですが、未経験者でも始めやすい仕事といえるでしょう。向いているのは、人と話すのが好き、接客が苦にならない、お客様の身になって応対ができる人です。
報酬は時間給で設定されていることが多いですが、まれに1本あたり○円と受けた本数により計算される場合があります。なお、同じカスタマーサポートのなかでも技術的なお問い合わせを専門に受ける仕事は、テクニカルサポートなどと呼ばれることがあります。
具体的にはそこの企業が取り扱う機器やアプリケーションの操作を教えたり、トラブル発生時に電話で対応をするといった仕事です。
一般的なお問い合わせよりも難易度が高いということで、報酬額も高めに設定されていることが多いです。とはいえ、最初からそこの商品をすでに知っている、もしくは技術的な知識を持っているといった必要はありません。
研修やマニュアルが用意されていることが多いため、お問い合わせ者の話を聞き、マニュアルに従い対応すれば、スムーズに解決できることがほとんどであるためです。どちらの案件も、在宅ワークを取り扱う求人情報サイトで見つけることができます。
ママワークスでお仕事を探す

8.コールスタッフ
お客様からのお問い合わせを受けるのがカスタマーサポートであるのに対して、架電をしてお客様に商品やサービスを案内するのがコールスタッフの仕事です。顧客を獲得するのが目的なので、いわゆる電話で行うセールスといえるでしょう。
報酬は1件あたり○円と単価制のケースがほとんどです。リストに基づいて電話をかけていくだけなので、難しいことはありません。トークスクリプトも用意されているので、人と話すのが苦にならない人ならこなせるでしょう。
もし、相手が商品に興味を持ち説明を求めてきた場合は、別のスタッフにコールバックなどの対応依頼を行います。その際はインセンティブとして別途報酬が設定されていることが多いです。仕事は、求人情報サイトで見つけることができます。
ママワークスでお仕事を探す
9.オフィスサポート(経理・人事・労務)
どこの企業にもつきものの事務業務を代理で行うのがオフィスサポートです。最近はICTの発展により、経理や人事、労務、営業事務などその範疇が広がっています。経理であれば帳簿をつけたり、支払いを確認したり、決算処理を行いますし、人事労務であれば人の管理、給料の計算、福利厚生の手続き、人材育成業務などがあります。基本的には、前職での経験を活かして、前職と同じ業務を請け負うことがおすすめです。
ママワークスでお仕事を探す
10.翻訳
翻訳は英語や中国語などの外国語を日本語に訳したり、逆に、日本語を他の国の言語に訳す仕事です。最近は商品やサービスがますますグローバル化しており、翻訳のニーズも増えています。
AIを使った翻訳サービスが開発され、ニーズが減少傾向にあるといえますが、それでもなお、AIではまだ追いついていない分野や領域があるため、在宅翻訳家への案件も多数見つけられます。なお、報酬は1文字あたり○円といった単価制の場合が多いです。
納期までに納品すればいいので、好きな時間に作業することができるため、子育て中のママや副業としてもおすすめです。なお最近は、中国語、韓国語、フィリピン語など、アジア圏の翻訳の仕事が急激に増えています。
世界共通言語である英語の案件が圧倒的に多いですが、得意とする方も多い分、相当な言語力が求められます。個人事業主としてやっていく場合、翻訳事務所に登録したり、求人情報サイトで案件を探すとよいでしょう。
ママワークスでお仕事を探す
まとめ
個人事業主は税務署に開業届を提出して事業所得を得ている人を指し、フリーランスは特定の会社に属さない働き方、自営業は自分で事業を営むことを意味します。個人事業主になるには開業届の提出が必要ですが、誰でもなることが可能です。好きなことを仕事にでき、努力次第で収入アップも可能なため、大きなやりがいを感じられるでしょう。一方で収入が不安定になりやすく、社会保険や福利厚生が薄い点はデメリットです。インボイス制度や補助金、確定申告についても理解を深め、自分に合った働き方を選択しましょう。







